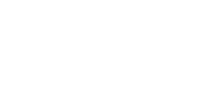誰もがAIを使える時代に、次の一手はあるか?
2025年、生成AIの世界は明らかに次のフェーズに突入しました。ChatGPTをはじめとした生成AIツールが広く普及し、「誰でも使える」ことはもはや前提条件になりつつあります。しかし、多くの企業で見られるのは「導入はしたが活用が続かない」「どこに使えばいいか判断がつかない」といった課題です。実際、JUAS(日本情報システム・ユーザー協会)の調査では、生成AIを導入した企業のうち、約38.7%が「効果が出なかった/PoCで止まった」と回答しています。
では今、企業に求められるのは何でしょうか? 本記事では、生成AIの自由化が進む中で、戦略的に次の一手を打つための視点を探ります。
なぜ今、「AI探索元年」なのか
2024年後半以降、主要な生成AIベンダー(OpenAI、Anthropic、Google、Metaなど)は、自社モデルのAPIや機能を積極的に開放。実際、OpenAIのAPI提供件数は2024年比で約1.7倍に増加したと報じられています。さらに2025年には、OpenAIがライバルであるAnthropicの標準仕様「Model Context Protocol(MCP)」を採用し、複数のAIモデルが同じデータソースに接続可能となるなど、生成AI間の相互運用性が飛躍的に向上しました。
これは裏を返せば、「ツールは揃ったが、活かすも殺すも使い手次第」という時代に入ったということです。こうした中、「探索(Exploration)」というキーワードが浮上してきました。
探索とは、業務や事業の中で「AIが何に使えるかを見つけに行く行為」です。完成されたユースケースではなく、仮説と検証を繰り返す試行的なプロセスです。
企業が取り組むべき3つの探索ステップ
この「探索元年」を成果につなげるには、以下の3ステップがカギとなります:
- まずは“どこに使えそうか”を見渡す
- 日常業務の中で、「時間がかかっている」「マニュアル化されていない」と感じる作業を洗い出してみましょう
- そこにAIを補助的に活用できる場面がないかを、ざっくり検討してみることから始められます
- スモールスタートでの社内PoC実践
- 完全自動化ではなく、半自動や補助的な使い方からスタート
- 例えば:営業資料作成、顧客対応履歴の要約、FAQの自動生成など
- 外部パートナーとの探索的対話
- 実践経験のある外部人材やベンダーと対話を重ねることで、視野を広げる
- 伴走支援を受けながら仮説→実験→評価のプロセスをまわす
よくある落とし穴:現場の一部だけでツールを試して終わりにしてしまい、全社展開できない。成功には、上流設計と運用定着の両輪が必要です。最新の調査によれば、PoCを実施した企業のうち67%が本番環境に移行できていないというデータもあります。
現場から見えてきた「探索型AI活用」
たとえば、ベテラン作業者のノウハウ継承に課題がある製造業では、AIチャットボットにQ&A履歴を学習させることで、若手社員が「これはどうやるの?」と尋ねれば適切な回答が返ってくる環境を整えることができます。
こうした活用により、OJTの効率化や人材教育の標準化が進み、現場の生産性向上に寄与する可能性があります。探索から始めた試みが、やがて組織の“次世代教育システム”へと発展することも期待されます。
まとめ:生成AIは、戦略なしでは活かしきれない
生成AIが「誰でも使える」ものになった今、次に問われるのは「どう使い続けるか」「どの業務に効果があるか」という視点です。
探索元年のいまこそ、仮説検証を繰り返しながら自社に合った活用法を模索することが、差別化のカギとなります。
☞ 株式会社YEAAHでは、AI活用や導入の支援を実施しています。
詳しくは、DX伴走支援サービスページをご覧ください。
出典一覧
- JUAS, 『企業IT動向調査2025』(引用元:WEEL)
- Axios, “AI industry growth accelerates in 2025: API usage trends”
- TechCrunch, “OpenAI adopts rival Anthropic’s standard for connecting AI models to data”
- Arpable, “国内AI市場の未来予測 2025年最新調査”
- YEAAHブログ 『生成AI疲れを乗り越える“探索フェーズ”とは』
Q1.生成AIの導入はどこから始めればいいですか?
まずは、業務の中で「どこに使えそうか」を見渡すところから始めましょう。
Q2.PoCで終わらせないためには、どうすればいいですか?
PoCの結果をもとに、次の改善や導入フェーズを見据えることが大切です。
Q3.業務を棚卸ししたり、マッピングする必要はありますか?
本格的な棚卸しは不要です。ざっくりと業務を見渡すだけでも十分です。
Q4.専門人材がいなくても生成AIの導入は可能ですか?
はい。現場の課題が明確であれば、専門知識がなくても始められます。
Q5.導入にあたって外部の支援は必要ですか?
自社だけで進めるのが難しい場合は、外部との探索的な対話が有効です。