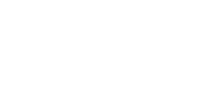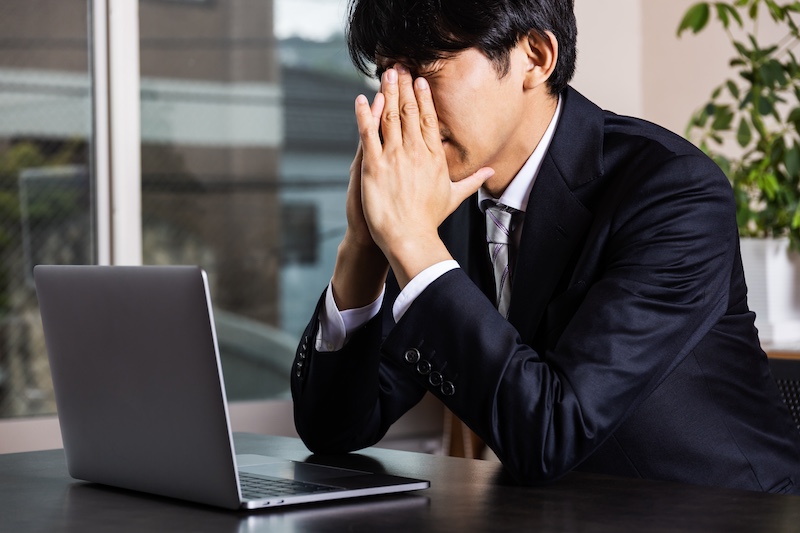1. 気づいたら、毎日のように使っていた
私は日常的にChatGPTを使っています。資料の構成を考えたり、メールの表現を整えたり、アイデアを練ったり。気づけば、ほぼ毎日のように活用しています。
そんな自分にとって、「生成AI疲れ」という言葉を初めて見たときは、正直「えっ?」と驚きました。使えば使うほど便利になっている感覚だったので、疲れるという実感があまりなかったのです。
でも、少し調べてみたり、実際にそう感じている人の記事や声を読んでいくうちに、「ああ、これは確かにあるかもしれないな」と納得感も湧いてきました。
なお、本記事では例としてChatGPTを多く扱っていますが、ここで述べる“疲れ”の構造は、CopilotやNotion AI、Claudeなどを含む他の生成AIツールにも共通する傾向です。
本記事では、その気づきをもとに、「なぜ生成AIで疲れるのか?」「疲れない人と何が違うのか?」を、自分の経験も交えながら考えてみたいと思います。
2. 生成AI疲れとは?心理的な負担が起こる理由
noteやZenn、SNSなどに投稿されたChatGPT活用の実体験からは、以下のような悩みが共通して挙げられています。
「プロンプトを毎回考えるのがしんどい」
「出力された文章を直すのに結局時間がかかる」
「使ってると、かえって判断がぶれる」
「上司に“これAIが書いたの?”と微妙な空気に」
一見、便利なはずのツールが、むしろストレス源になってしまう。
それはなぜなのでしょうか?
3. なぜ生成AI導入で“新しい業務”が生まれるのか?
生成AIの導入によって、実際には以下のような“新しい業務負荷”が発生していることが分かっています:
| 発生している“新たな業務” | 内容 |
| プロンプト設計 | 目的に合う出力を得るための入力調整・ライブラリ管理 |
| 出力レビュー・修正 | 文脈や誤りをチェックして、実用レベルに整える作業 |
| ルール整備・研修 | 利用ガイドライン作成やセキュリティ教育など |
| 成果の可視化 | 「本当に効率化できたのか?」のKPI設計・報告 |
| 応答疲れへの対策 | AIとの対話における心理的・認知的な疲労の緩和 |
実際、Campus Technologyの調査(2025年)では、従業員の77%がAI利用後の仕事量が増えたと感じており、“AIテクノストレス”を経験していると報告されています。
4. 生産性の影に潜む“生成AIの副作用”とは?
生成AIの登場によって、多くの業務で「スピード」や「アウトプットの量」が格段に向上しました。
しかしその一方で、数字には現れにくい“心理的な副作用”も見逃せません。
たとえば、Zhejiang大学の研究(HBR掲載、2025年)では、生成AIを使うことで作業の品質とスピードは上がる一方、内発的動機が低下し、仕事への興味を失いやすくなることが報告されています。
また、Forbes(2025年6月)では、「AIに任せればいい」という空気が強まる中で、人間側が意思決定を避ける傾向が出てきており、それが結果として“判断疲れ”や“責任の曖昧さ”を引き起こしていると指摘されています。
さらに、McKinseyの2025年レポートでは、AIを使いこなす人とそうでない人の間に「業務スピードや質の格差」が生まれており、社内に“焦り”や“孤立感”を生む原因になっているという警告も示されています。
こうした傾向は、日本国内でも少しずつ指摘され始めています。
たとえば、パーソル総研による若手社員の調査では、週52時間以上の画面業務を行う層で脳疲労リスクが約1.5倍になっているとの結果が出ており、生成AIの活用によって作業時間や判断負荷が増している可能性が示唆されています。
また、noteやZennなどでは、実務者やリサーチャーによってこんな声も紹介されています。
- 「AIのアウトプットが早すぎて、常に“判断”を求められて疲れる」
- 「複数のAIを使い分けるうちに、タスクの切り替えやレビューが“地味に消耗する”」
これらは単なる感覚的な愚痴ではなく、生成AIが業務に深く入り込むからこそ生まれる“新しい種類の疲労”なのかもしれません。
5. ChatGPTで“疲れる人”と“疲れない人”の違いとは?
私自身、そこまで疲れを感じていなかったのかを考えてみました。
たぶん、「こういうことをしたい」「ここを整理したい」といった方向性や判断基準を自分の中に持っているからだと思います。
逆に言えば、方向性がないままAIを使い始めると:
- 何を聞けばいいか分からない
- 出力が使えるかどうかの判断が難しい
- 修正を重ねるうちに、むしろ疲れてしまう
という“認知的負荷”が大きくなってしまうのです。
6. なぜ「問いを持つ人」はAIに疲れにくいのか?
生成AIは「なんでも教えてくれる魔法の道具」ではありません。
むしろ、「何を聞きたいかを持っている人」にこそ、最大の力を発揮するツールです。
これは、AIリテラシーというよりも「思考の軸」の話かもしれません。
- 目的があるから、出力の質を評価できる
- 判断基準があるから、活用できる
その前提がある人にとって、AIは本当に心強いパートナーになり得ます。
7. とはいっても「問いを持つ人」でもAIに疲れる??
しかし、改めて色々調べていくなかで共感した点として重要なのは、「問いがあれば疲れない」わけではないということです。おいおい、言ってること矛盾しているじゃないか!と思うかもしれませんがそうですよね。。
最近では問いを持ち、生成AIを日常的に使いこなしている“上級者”のほうが深い疲れを感じているケースもあるようです。
noteやZennに投稿された体験談でも、「緻密なプロンプトを毎回考えるのがしんどい」「レビューと判断を繰り返すうちに神経が磨耗する」といった声が多く見られました。
8. なぜ「問いを持つ人」もAIに疲れるのか?
これは、「生成AIが便利すぎる」ことの裏返しでもあります。
AIはどんどん高性能になり、アウトプットのスピードも質も上がっている。
それに応じて「もっと早く」「もっと正確に」「もっと使えるものを」という期待やプレッシャーも高まっています。
さらに、AIによって業務そのものの範囲や役割が広がったという側面もあります。
以前なら考えなかったドキュメント設計、提案作成、文章表現のチューニングまで、AIが使えるからこそ「やって当然」という空気が生まれる。
そうなると、プロンプトは1回で済まず、何度も調整し、判断し、細かく修正する——
疲れないはずがありません。
問いがあることは大切ですが、それは“便利に使いこなす条件”ではなく、疲れと付き合うためのヒントくらいに思っておくのが現実的かもしれません。
生成AIに“完璧な出力”を求めすぎないことは大切です。
ただし、それは「どんな出力でも受け入れる」という意味ではありません。
特に画像や動画、営業資料など“完成度が問われる成果物”においては、一発で理想のアウトプットを得ようとするほど、調整作業が増え、疲労感も蓄積します。
こうしたときに有効なのが、「AIだけで完結させない前提で設計する」ことです。
たとえば、AIには“ラフ案の生成”まで任せ、その後の修正・仕上げは人が担うと最初から決めておくことで、過剰なプロンプト修正や“出力に対するがっかり感”を回避できます。
生成AIはあくまで“共創の相手”であり、人間との役割分担が前提のツールなのだと思います。
9. 「うまく使えない」人が悪いわけではない理由
今、生成AIをうまく使いこなせていないと感じている人がいたとしても、それは“能力が足りない”わけでも、“リテラシーが低い”わけでもないと思うのです。
もしかしたら、まだ「自分の問い」が育っていないだけ。そして、その問いは日々の試行錯誤のなかで、少しずつ見えてくるものでもあります。
だからこそ、うまく使えている人は、自分のやり方を押しつけるのではなく、「こう考えるとラクになるかもしれない」という共感と視点のシェアが大切なのだと思います。
そして、そのリテラシーが高いはずの方にとっての落とし穴が「完璧な出力を期待してしまう構造」や、「使って当然」という空気そのものが疲れの元になっている面もあるのではないでしょうか。
大切なのは、「うまく使うかどうか」ではなく、自分なりに“どこまで任せるか”を考え、“力を抜ける設計”をしておくこと。生成AIとの関係は、最適解を探すものではなく、自分にとって無理のない距離感を探す“設計”に近いのだと思います。
10. おわりに一言
生成AIに疲れることは、ある意味“当たり前”のことかもしれません。
でも、その中でも「少しだけ楽にする工夫」や、「疲れを共有できる環境」は確実に存在します。
疲れと無理なく付き合っていくには、“完璧”を目指すのではなく、“自分なりの設計”を探していく。
そのプロセスを一緒に考えることこそ、今、私たちができる最良のアプローチなのだと思います。
✅ 参考文献一覧(すべて2025年)
- Harvard Business Review(2025年5月)
- Campus Technology(2025年6月)
- Forbes(2025年6月24日)
- McKinsey & Company(2025年6月)
- Smart相談室(パーソル総研, 2025年6月)
- note:堀聡太氏(2025年)
- Zenn開発者エッセイ(2025年)
よくある質問(FAQ)
Q.生成AIで“疲れる”とは、どういう状態を指しますか?
A. 主にプロンプト作成や出力のレビュー、判断の連続による心理的・認知的な疲労を指します。物理的な作業量よりも“頭を使う負荷”が多いのが特徴です。
Q.ChatGPT以外のAIでも同じような疲れはありますか?
A.はい。Copilot、Notion AI、Claude、Geminiなどでも同様の構造的負荷が報告されています。特にタスク切り替えや複数AIの併用による判断疲れが見られます。
Q. 疲れないためにはどうすればいいですか?
A. まずは、「目的を明確にする」「判断軸を持つ」「使わない日をつくる」などが有効です。そして「AIに任せる範囲を決める」「期待しすぎない」「疲れたときに手を止める」など、自分に合った“使い方の設計”を意識することも大切です。
Q. AIに“完璧な答え”を期待しない方がいいのはなぜ?
A. 出力に対して期待しすぎると、「違うな」と思うたびにストレスを感じたり、修正を繰り返すことで疲労感が高まります。AIには“7割の叩き台”として期待し、自分で補正していく前提で向き合うほうが、精神的にも安定して活用できます。
Q. 画像や動画のように、AIに完成度の高い出力を求める場面ではどうすればいいですか?
A. 完成度が求められる成果物では、「AI+人の分業設計」が効果的です。AIにはラフ案を任せ、人間が仕上げを行う前提で設計することで、AIに“完璧な一発回答”を期待しすぎず、結果的に効率も品質も安定します。
株式会社YEAAHでは、生成AI活用における“問いの設計”と“疲れない使い方”も支援しています。
「なんとなく使いこなせない」「導入したけど活用が進まない」などのお悩みがある方は、ぜひお気軽にご相談ください。